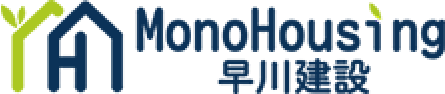2025年3月26日
コラム
2025年4月以降の木造2階建て住宅建築に義務化である構造計算書の基礎知識

2025年4月、建築基準法の改正により、木造2階建て住宅の建築確認申請において構造計算書の提出が義務化されます。
この変更は、住宅建築やリフォームを検討されている方にとって、大きな関心事と言えるでしょう。
今回は、この改正の概要、影響、そして注意点などを解説します。
2025年4月以降の木造2階建て構造計算書 提出義務の概要
改正の背景と目的
2025年4月の建築基準法改正は、省エネルギー基準の義務化と耐震性の強化を主な目的としています。
省エネルギー基準の義務化は、地球温暖化対策の一環として、住宅の断熱性能向上を促すものです。
一方で、耐震性の強化は、近年増加する地震災害への対策として、住宅の構造安全性を高めることを目指しています。
これらの目的達成のため、これまで一部省略されていた構造計算書の提出が義務化されました。
対象となる木造2階建て住宅の範囲
改正により、構造計算書の提出が義務化されるのは、主に木造2階建て住宅です。
ただし、延床面積や高さによっては、対象外となる場合もあります。
具体的な範囲については、国土交通省の資料などを参照することをお勧めします。
平屋建て住宅については、延床面積が200㎡以下の場合、従来通り構造計算書の提出は不要です。
構造計算書の提出義務化の詳細
2025年4月以降、木造2階建て住宅を建築する場合、建築確認申請において構造計算書を提出することが義務化されます。
これは、住宅の構造強度が建築基準法に適合していることを証明するためのものです。
構造計算書には、建物の耐震性、耐久性などを検証した結果が記載されます。
必要な手続きと流れ
構造計算書の提出が義務化されたことにより、建築確認申請の手続きが複雑化します。
設計段階で構造計算を行い、その結果を基に構造計算書を作成します。
その後、建築確認申請に必要な書類を揃え、所轄の行政機関に申請を行います。
申請が受理されると、審査が行われ、問題なければ建築許可が下りる流れです。

構造計算書提出義務化による影響
建築費用への影響
構造計算書の提出は、建築費用の上昇につながる可能性があります。
構造計算には専門家の費用が必要となるため、設計費用が増加します。
また、計算結果によっては、構造補強が必要となるケースもあり、追加費用が発生する可能性も考慮する必要があります。
建築期間への影響
構造計算に時間を要するため、建築期間の延長も予想されます。
設計段階での計算、審査機関への申請、そして結果の反映など、各段階で時間が必要となります。
余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
建築業者への影響
建築業者にとっては、構造計算の対応が新たな業務負担となります。
専門知識やソフトウェアの導入、人員確保など、対応するための投資が必要となるでしょう。

2025年4月以降の木造2階建て住宅建築・リフォームにおける注意点
建築確認申請の手続き
建築確認申請は、建築基準法に則って行われる手続きです。
申請書類は複雑で、必要な書類を漏れなく揃える必要があります。
専門業者に依頼することをお勧めします。
省エネルギー基準への対応
省エネルギー基準への適合も義務化されています。
断熱性能、気密性能などを考慮した設計・施工が必要となります。
まとめ
2025年4月からの建築基準法改正により、木造2階建て住宅の構造計算書の提出が義務化されます。
これは、住宅の安全性と省エネルギー性能の向上を目的とした改正です。
建築費用や建築期間への影響も考慮し、信頼できる建築業者を選定することが重要です。
改正内容を理解し、適切な手続きを進めることで、安心して住宅建築やリフォームを進めることができます。
今回の改正は、住宅の品質向上に繋がる重要な取り組みであり、長期的な視点で住宅の価値を高めることに貢献するでしょう。
館山市・南房総市・鴨川市周辺で家を建てることをご検討の方は、MonoHousing早川建設へどうぞ。